伊集院さつき編
「封印された扉」前半
「ハァッ!」相手選手の気迫のこもった一撃を放つ。伊集院さつきはそれを軽やかにかわし、一気に距離を詰めた。ティー・ソークで反撃しようとした相手の懐に一瞬にして潜り込み、両腕で首をガッチリとホールドする。完璧な首相撲の体勢だ。「おやすみ♪」さつきは相手の耳元でそう囁くと、相手の上体をぐっと引き寄せた。「ヒュッ」口笛のような鋭い息がさつきの口から漏れ、次の瞬間にはさつきの右膝が、相手選手の肝臓に深々と食い込んでいた。
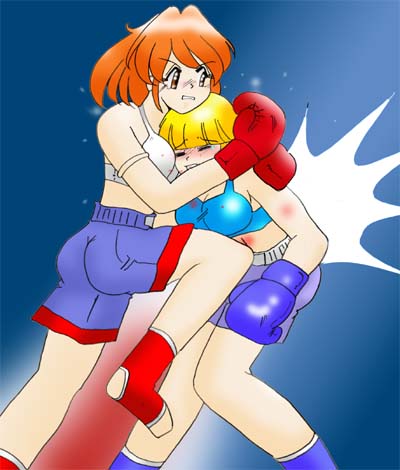
「ブゥウグアァァ…」断末魔のような声にならぬ声が上がる。さつきは必殺の膝を叩き込むとさっとバックステップを踏んで距離をとった。相手選手の目からは精気が失せ、マウスピースがだらしなくはみ出しかかっている。両腕もダラリと垂れ下がり、まるで酔っぱらっているようだ。このまま放っておいても、ひとりでにキャンバスに沈むのは誰の目から見ても明らかだった。
しかしレフリーがストップをかけるより、さつきの右アッパーが遙かに速かった。「ガズン」鈍い衝撃がさつきの右の拳に伝わり、勝利の快感とともにさつきの全身を駆けめぐった。右グローブに相手選手の顎を乗せたまま、さらに力を込めて突き上げる。「ブッバァァ!ァァ…」おびただしい唾液が飛び散り、吐き出されたマウスピースがまぶしいライトの光の中に吸い込まれて消えた。「ガダァン」相手選手の体が激しくキャンバスに打ち付けられた。「ゲェッ、ウボッ…」二、三度呻き声が漏れる。「ビシャァ」ネットリとした唾液を一杯に身にまとったマウスピースが長い空中遊泳を終え、さつきの右頬をかすめてキャンバスに転がった。KOされた対戦相手は白目をむき、思い切り両手足を伸ばしたまま、口元に泡をためて失神している。ビクン、腰のあたりを一度痙攣させるともうそれっきり動かなくなった。
「よーし!今日も絶好調!!」さつきは大歓声をあげる観客に右腕を突き上げて応えた。さつきの体にはほとんど汗が浮いていない。キックの試合はこれで6戦目、すべてKO勝ち。なんといっても、相手にとどめの一撃を加える瞬間は、何ともいえない甘美な瞬間だった。殺気を込めて向かってくる相手が、さつきの猛攻の前に力つき、無防備な隙をさらけ出す。そこへどんな一撃を加えようと、さつきの思いのままだった。幼いときから空手で鍛えられたさつきのパンチ・キックの破壊力は女子選手の水準を遙かに凌駕する。今日「生贄」になった選手もまだ失神したままで、ちょうどセコンドたちによって担架に載せられるところだった。
「いや〜ぁ、すばらしいKO勝ちでしたね。いつもながら見事なKOショーを見せてくれますね!」
インタビューの記者が興奮気味に言った。「ありがとうございます。」さつきは満足して応える。「本当に伊集院さんの『桜島アッパー』の破壊力はすさまじい!」『桜島アッパー』と言われ、さつきはちょっと眉を顰めた。いくら自分が鹿児島出身で、アッパーが得意だからといって、『桜島アッパー』
なんて、なんて安直な…もうちょっと気の利いたネーミングを考えてよ!腹の中でそう思ったが、口には出さなかった。「こんどは女子総合異種格闘戦『バルキュリー』に出場とのことですが、自信のほどはいががですか?」記者の言葉通り、さつきは2ヶ月後に開催される女子異種格闘技大会にエントリーしていた。「ええ。今までマスターした格闘技を全部活かして、全力でがんばります!」「『がんばります』とは控えめですね。」記者は明らかにある発言を期待している。ようし!それならご希望に応えてあげるわよ。「もちろん出場するからには優勝を狙います!」さつきがこう答えると、大歓声が会場を揺るがした。「それでは伊集院選手の、世界を相手にしたKOショーを期待しています!」インタビューが終わるとさつきはもう一度右のグローブを突き上げ、観客に応えた。
「ふうぅっ」ドレッシングルームに戻り、ベンチに腰を下ろした。「優勝宣言とは大きくでたな」さつきのグローブの紐を切りながらジムの竹中会長が苦笑混じりにいった。「でも、あの人そういうのを期待してましたよ。私はそれに応えてあげただけです。これもプロの仕事ですからね。」「まあそれはそうだが…」小さいときからさつきの指導に当たっている会長が言葉を切った。この娘の気の強さは人一倍、いや五、六倍あるかもしれないな…そう思うとさらに苦笑が漏れる。「どうしたんですか?」さつきが不思議そうに聞いた。「いや、何でもない。いいか、明日からルールの確認と調整にはいるから、今日はさっさと休めよ。キック以外の技は錆び付いちゃいないだろうな?」竹中がそういうと、さつきはグッと腕を曲げ、力こぶをつくって見せた。「任せてください!」そういうさつきの額を会長がちょこんと小突き、さつきの口元が少し緩んだ。
『バルキュリー』が戦いの女神の名前であるように、今回の大会では世界中の女子格闘家が一堂に集い、世界最強を競う大会である。優勝賞金は3000万。賞金といい規模といい空前の大会であった。体重無制限。パンチ・キックといった打撃ばかりではなく、関節あり、投げありで、すべての攻撃が認められた文字通り格闘技の祭典である。この大会でさつきの最初の対戦相手は、シュートボクシングの三倉明美。シュートで8戦全勝5KO。グラビアのタイトルも何回か飾ったことがあるだけに、キリッとした相当に美形の選手である。さつきはこの選手が嫌いで仕方がなかった。全くちゃらちゃらして、恥ずかしいったらありゃしないわ。格闘技を舐めきってるんじゃないの?ほとんど嫌悪に近い感情を抱いていた。
さつきの表情が険しくなったのを敏感に感じ取った竹中会長がいう。「最初からいい組み合わせじゃないか。」さつきがキッとした表情で会長を見た。この娘は感情を隠すのが本当に下手だ。全くのせやすい。「ええ、いい気になってることを後悔させてあげますよ!」「ようし!じゃあ、まず投げと関節のチェックから行くぞ。」そういって会長はリングに上がり、さつきも後に続いた。
試合当日、リングに上がったさつきの仕上がり具合は完璧だった。全身に気力が漲っている。リングの向こう側では、三倉が両腕をあげ、観客の声援に応えている。全く愛嬌振りまいちゃって…試合が終わった後もその元気があればいいげどね。さつきはそう思った。
試合開始のゴングと同時に、三倉はキック戦を挑んできた。「キックボクサーにキックで挑むなんて…なめてくれるわ!」さつきも真っ向から応じ、激しいキックが応酬される。しかしこの緊張も長くは続かなかった。さつきのキック力は三倉を遙かに上回り、たちまちロープに追いつめてしまった。「ビシッ!」さつきのローが三倉の太股に決まり、真っ赤な痣がまた一つ花開いた。バランスを崩した三倉に素早いジャブが飛ぶ。「ブゥ!」三倉の顔面にまともにヒットし、彼女の美しい顔が醜く歪む。更に連打を叩き込もうとしたさつきを、三倉の両腕がガッシリと捕らえた。「ヤアァア!」三倉の口から鋭い声が漏れ、首投げの体勢に移行する。投げならシュートの独壇場である。形勢が逆転する!誰もがそう思ったが、さつきは素早く体を入れ替え、逆に相手の首をホールドし、そのまま頭からキャンバスに叩き付けた。「ドガァ!」三倉の頭がキャンバスに激突し、激しい音を立てた。「ウゥ、ウッ…」三倉の形のよい唇から弱々しい声が漏れる。とたんに動きが鈍った三倉をグラウンドに持ち込み、スリーパーで締め上げる。この一瞬の早業は、さつきの天性の格闘センスを何よりもよく物語っていた。三倉は必死にさつきの腕を引きはがそうとするが、顎にガッチリ食い込んださつきの腕はビクともしなかった。「げふっ、ゴホォッ!」三倉が激しく喘ぎ、両足をバタバタさせる。よだれがさつきの腕に垂れ、腕を伝ってゆっくりとキャンバスに吸い込まれていく。グラウンドの時間は20秒。その間にギブアップしなければ、ブレイクが命じられ、スタンドから試合が再開される。その20秒が過ぎる1秒ごとに三倉のスタミナが消耗し、確実にゼロに近づきつつあった。「大丈夫よ。」さつきが三倉の耳元で囁いた。「もっと気持ちよ〜く楽にしてあげる。」更に三倉が足をばたつかせたところで、20秒が経過し、彼女を地獄の苦しみから救った。「スタンド!」レフリーの声にさつきはさっと立ち上がったが、三倉はキャンバスに跪いたまま、歯を剥き出しにして喘いでいた。「ゴホッ、エゴッ!ブハァッ!!」おびただしい唾液にまみれたマウスピースが吐き出され、キャンバスにぶつかって大きくバウンドした。「ガハッ、ううぅ」三倉の両肩が激しく上下し、時折激しく咳き込む。しかし三倉明美もシュートボクサーとして修羅場をくぐり抜けてきた強者である。その目には依然として闘志の炎が消えることがなかった。膝をついたまま、さつきに鋭い視線を送っている。
「ふう〜ん。アイドルさんも結構意地があるのね。見直してあげるわ。」さつきは思った。「後一発で終わるわね。」この考えは間違っていない。三倉の闘志は相変わらず燃えたぎっていたが、スタミナは完全に尽きていた。一発小突いただけでも、レフリーは試合を止めるだろう。「楽しませてもらうわよ♪」そう思ったさつきの頬を三倉のパンチがかすめる。さつきにとっては蚊の止まるようなパンチだ。三倉の足は、さつきのキックでフットワークすらままならないダメージを受けていた。もはやこの「蚊の止まるような」パンチが三倉のすべてだった。さつきの神経が針のように研ぎ澄まされていく。さつきの視線はずっと三倉の顎を追っていた。まるで高性能の戦闘機が、敵機をレーダーロックしているかのようだ。三倉の顎がさつきの予測した軌跡と完璧に一致した。ロックオン!「今だ!!」この瞬間さつきは一陣の風になった。グッと三倉の前に沈み込み、膝と腰、腕の力、すべての力が込められたグローブをすさまじい勢いで突き上げた。

「グジャァッ!」骨の砕ける音が会場に響き、何人かの女性が音程の外れた悲鳴を上げた。三倉の顔がまるでプレスされたように上下にひしゃげた。さつきの全身をいつもの快感が駆け抜ける。そのままグローブを突き上げた。三倉がつま先立ちになり、体が宙に舞った。「グボッ」三倉の口から真っ赤な固まりが吹き上げられる。さまにいま『桜島』が大噴火したのだ。吐瀉物が爆発的に放射され、その中をマウスピースと砕き折られた何本もの歯が、まぶしいライトの光を浴び、妖しい輝きを放った。「ガダァン!!」意識を失った三倉の肉体がもんどり打つようにキャンバスに叩き付けられる。レモンイエローのトランクスの上に、今まで宙に舞っていたものがキラキラ輝きながら降り注いだ。真っ赤な雫がまだらの模様を描く。「ぼとん」マウスピースが三倉のベルトラインのあたりに落ち、一回だけバウンドして身にまとった血反吐を脱ぎ捨てると、ズルズルとキャンバスに転がり落ちた。いつもなら大満足を感じるはずだった。しかしこの三倉明美の無惨な姿は、さつきの心にいつもと違った異常な後味の悪さを刻み込んだ。大の字のまま仰向けになっている三倉が激しく痙攣する。何より衝撃的だったのは、彼女の顔だった。グラビアを飾っていたあの三倉とは似ても似つかぬ顔がそこにはあった。顎の骨を粉砕され、だらしなく口を開けている。信じられないほど舌が長くのぞいている。折れた歯が、歯茎から垂れ下がっていた。「グバァッ、ガァ!」意味もないうめきが漏れた。垂れ下がっていた歯が歯肉ごと、音もなくこぼれ落ちる。「ビクン!」三倉がひときわ激しく痙攣して硬直したかと思うと、全身から力が抜けそれっきり動かなくなった。
「!」三倉のうつろな目を見た瞬間、さつきの体が硬直した。「この目…」何かこの目には覚えがある。あれはだいふ前に…そうだ!小さいときに、近所の悪戯坊主と一緒に野山を駆けめぐっていたときだ。あのとき友達が面白半分に殺した蛙と同じ目だ。『なんで私を殺したの?私が何をしたというの?』そのとき幼いさつきは、間違いなくその蛙の声を聞いた。そのことで悪夢にうなされ、幾晩泣きわめいただろうか?心の奥底から、嫌な思い出をひっくるめて押し込んでいた記憶の暗部から、もっとも思い出したくない記憶が鮮明に蘇り、さつきは体がぶるぶる震えるのを止めることができなかった。
「ドクターを!!」会場が騒然となった。ドクターがリングに駆け上がり、呆然と立ちすくんでいるさつきを押しのけ、三倉の元に駆け寄った。さつきはまるで強打を浴びたかのようによろめいた。「おいどうした?」竹中会長に声をかけられ、はっと我に返る。「これはひどい!顎が完全に砕けてる!!」救急車を呼べ!」ドクターの声が全く現実感を伴わずに耳に入ってくる。「頭を動かすな。脳内出血の可能性あり。レベル400!」ドクターの声がさつきの耳に突き刺さる。知らないうちにさつきの頬を涙が伝っていた。「わたし…わたし……」言葉が出ない。「おまえが勝ったんだぞ。どうしたんだ!?」会長がさつきの肩を激しく揺さぶった。会長と目が合うとさつきはリングの上にもかかわらず、会長にしがみついて激しく泣きじゃくっていた。
『三倉明美、壮絶な玉砕!!再起不能か?!』『桜島大噴火!伊集院さつきKOショーを展開!』次の日の新聞記事には昨夜の試合がでかでかと掲載されていた。あの『桜島アッパー』が三倉の顎を砕いた瞬間が全面に載り、その中にKOされて横たわる三倉の写真が何枚かちりばめられていた。三倉が白目を剥き、真っ赤な固まりを吹き上げている。そこに微かに笑みを浮かべてパンチを突き上げる自分がいた。さつきにはその写真に写っている自分が悪鬼のように見えた。「?」肩に手を置かれてさつきが振り返ると、そこには会長の竹中がいた。「あの…」さつきの声には力がない。「何だ?」「三倉選手どうなったんでしょうか?」会長が言いにくそうな表情をした。「まさか!?」さつきの背筋に冷たいものが走る。「いや。ただ再起不能だということは間違いない。でもな…」会長が言葉を句切った。「お前はきちんと試合をして勝ったんだ。なにも責任を感じることはない。お互いにそんなことは覚悟してリングに上がるんだ。立場が逆なら…」「わかってるんです。ただ…」さつきの言葉がとぎれた。「私はあのとき楽しんだんです。」「楽しんだって?」会長が聞き返した。「どうやってこの…、この嫌な女をぶちのめしてやろうかって…」さつきの口から嗚咽が漏れた。「そんな自分が恐ろしいんです。あんなパンチを叩き込まなくても勝てたのに…何であのとき、私…」さつきはそこまで言うと会長にしがみつき、子供のように泣きじゃくった。大粒の涙がさつきの目から溢れ、会長の服を濡らしていった。そんなさつきを会長は優しく抱き留め、背中をさすってくれた。
2戦目は、プロレスラーとの試合だったが、全く勝負と呼べるものではなかった。前の試合が出場選手たちに与えた精神的な衝撃は大きく、それはさつきに対する恐怖として具現化した。今日の対戦相手もさつきより頭二つ、体重にしてみれば3倍くらい体格で勝っていたが、完全に及び腰になっており、さつきのストレートが、たいして力のこもっていないストレートが腹に決まるとそれだけで戦意を喪失して、コーナーで背を向け、試合を放棄してしまった。
その後3連勝しても、さつきは勝利の快感よりも虚しさに支配されていた。試合中、あの三倉の恨めしそうな目が何度もフラッシュバックした。あんな悪鬼のような一面を自分が持っている。そう考えると、自分の体をバラバラにしてどこかに捨ててしまいたかった。自暴自棄になりながらも、敗北を喫することなく決勝まで勝ち進んでいったのは、さつきの格闘家としての本能が、さつきが今もっとも嫌っている、その残酷なまでの闘争本能がさつきを支えているのは、皮肉と言うほか無かった。「おい。もう自分を責めるのはよせ。」会長が声をかけた。「わかってます。そんなことはわかってるんです。ただ、頭でわかっていても何かが引っかかるんです。」さつき自身そのことをこの数ヶ月間、三倉明美を再起不能に追い込んだ時からずっと考え続けていた。頭では分かる。何のために自分は戦うのだろう?お金のため?いや絶対に違う!あのリングの上の緊張感、グローブを交えるときのドキドキするようなスリル。それが欲しい!!でも今の自分はそうしたものを感じられなくなってしまった…そんな煩悶がずっと続いていた。
会長はそんなさつきを慈しむような目で見たが、急に表情を厳しくして、クリップボードをさつきに手渡した。「決勝の相手が決まったぞ。」さつきはクリップボードに視線を落とした。
『「神鳥谷かすみ」春日部ボクシングジム所属。スーパーバンタム級。対戦成績 ボクシング:6戦全勝4KO バルキュリー:4戦全勝3KO』
「トータルで7KOか…。ボクサーがよくここまで勝ち上がれましたね。」さつきは率直な驚きを隠せなかった。足も投げも、関節なんかはもちろん関係ないボクサーが、ここまで勝ち上がれるなど信じがたいことだ。「『かみとりや』選手はどんなファイトスタイルなんですか?相当フットワークがないと、レスラーなんかに捕まるし、パンチがないとここまでKOは稼げないし…」
会長がさつきの言葉を遮った。「『かみとりや』じゃなくて『ひととのや』。お前の言うとおり、パンチ・フットワークともに最高水準だ。試合の組み立て方も並じゃないな。強敵だぞ。」さつきの目に輝きが戻ってきた。相手にとって不足はなさそうだ。この選手なら試合の充実感を、ここ数ヶ月全く感じることのできなくなっているあのゾクゾクするような感覚をよみがえらせてくれるかも知れない!そう考えると活力が戻ってくる。「望むところです。この『ひととりや』選手との日本人対決も最高ですよね!!。」思わず拳を握りしめてそう答えた。竹中会長の表情にさもおかしそうな表情が浮かんだ。「?」怪訝そうな顔をしたさつきをみて会長の口元が緩む。「お前さぁ、今なんて言った?」「えっ?」そんな変なことを言ったのかしら?「だから相手にとって不足はないって…」「ハハハハッハァ」会長が上を向いて大きな声で笑った。「会長!何がおかしいんですか!?私、真面目に言ってるのに!」さつきがムキになって言うのを聞いても会長の笑いは止まらなかった。「ハハハハ、いやそうじゃない。俺が聞いているのは対戦相手の名前だよ。」「だから『ひととりや』って」さつきがムキになって答える。「『ひととのや』だ。お前、対戦相手の名前を間違って何を力んでるんだ?」悪戯っぽい目でさつきを見た。「あっ!えっ!!その…あの…」とたんにしどろもどろになったさつきの顔が真っ赤になった。「お前は小さいときから物覚えがいまいちだったな。」「それじゃまるで私って馬鹿みたいじゃないですか!?」真っ赤な頬をふくらませ、口をとがらせてさつきが言った。「よし。それじゃあ、これなんて読むんだ?」会長が『神鳥谷』の字を指さしている。「うっ!ひと、ひと…」さつきがどもったように繰り返した。「うん、うん。どうも苦手なようだな。よしよし」まるで赤ん坊をあやすようにそういうとクリップボードの『神鳥谷』の上に「ひととのや」とルビを振った。「うっ、ぐっ!」言葉が出ないさつきの背中を会長は大きな掌で叩き、また大きな声で笑った。さつきもそれにつられ、思わず久々に明るい笑い声をあげていた。
フットワークは神鳥谷に譲るとしても、破壊力の点では自分が圧倒的に有利。さつきはそう分析した。キックの点では、下手に大振りなキックを放たなければ問題ない。懐に潜り込もうとしたら前蹴りで止める。作戦としては早いうちからローで神鳥谷の足を止め、ダメージを蓄積させて倒す。グラウンドに持ちこみ、関節でスタミナを奪えればいうことはない。試合の組み立て方を考えながらさつきは久々にワクワクする気分がよみがえってくるのを感じていた。決勝だからではなく、なんだかこの神鳥谷からは何かそうしたものを感じさせるものがあった。「ようし。頑張ってやるか!」そう独り言を言うと、さつきはロードワークに出ようとしてジムの扉を開け、外に出た。鹿児島の厳しい日差しにさつきは目を細め、右手をかざした。目の前には力強く噴煙を吹き上げている雄大な桜島が聳えていた。「頑張るからね!みててよ!!」桜島に向かってそういうと、さつきは軽快な足取りで風を切って走り始めた。