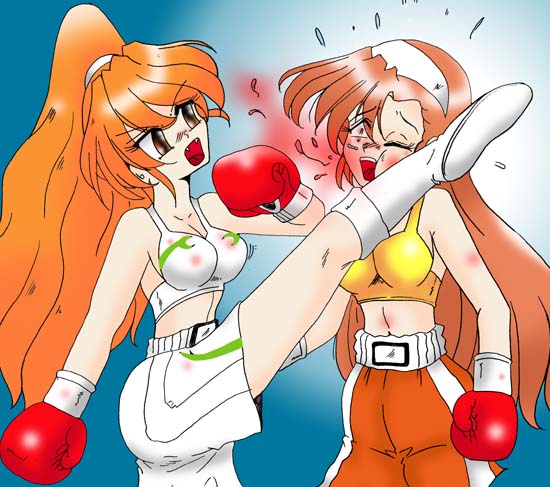戻る
裕子編『KOシスターズ!』「再戦」
『いかが?キャンバスの味は?』勝ち誇った声が頭上から響く。「?」目の前に純白のリングシューズがある。「えっ!何なの?」裕子がやっとの事で頭をもたげる。透き通るように白く、スラリとした足が見える。「ウグッ!」裕子は必死に体を起こした。
ひどく体が重い。「この声は!」裕子の膝がキャンバスから離れた。裕子の目の前には、茨をあしらった純白のリングコスチュームを身にまとった、ポニーテールの美少女が冷酷そうな笑みを浮かべながら立っていた。「ブラッディマリー!!」4戦目に対戦し、激闘の末KOしたはずの海老塚万里子がそこにいた。「なぜ?」裕子はまだ事情が飲み込めなかった。「私、この娘に勝ったはずじゃぁ…」朦朧としつつある意識の中で思った。辛うじてファイティングポーズをとるが、両腕が思うように動かない。「ファイッ!」レフリーの声を待ちかねたように、海老塚の猛攻が裕子を襲った。ガードがすべて後手後手に回る。「ウッ!」「グエッ」情けない呻き声が裕子の口から絶え間なく絞り出された。「狙うしかない…」ぼんやりと霞がかかったような頭で考えた。海老塚の右フックが風を切る。「ここだ!」裕子は最後の力を振り絞った右ストレートでカウンターを取りに行った。海老塚の姿が視界から消え、次の瞬間海老塚の右のグローブがすさまじい勢いで裕子の顎に食い込んでいた。「ブゲッ!」裕子は自分がマウスピースを吹き上げる音を聞いた。

裕子は酔っぱらったように前のめりになってふらつく。両腕がダラリと垂れ下がり、完全に無防備な状態だ。「まぁ…け、ない!」裕子の意識はそう叫んだが、もはや両腕には少しの力も入らなかった。ぼんやりとかすんだ視界の向こうに海老塚が、あの冷酷そうな笑みを浮かべて立っている。「これでも喰らいな!」彼女はそう言うと、全身のパワーを込め、十分にエネルギーを蓄積した右を、強烈な右のハイキックを繰り出した。
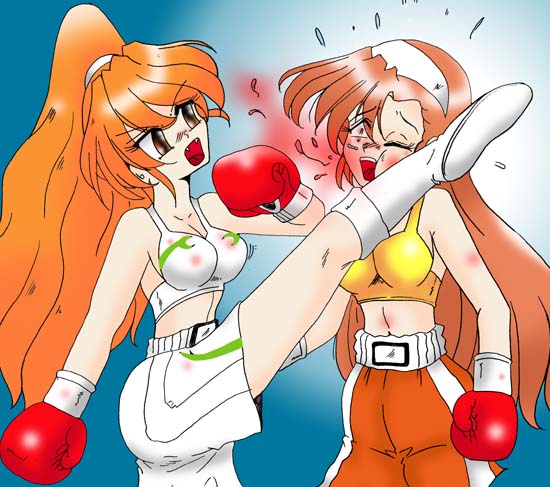
「ブバァッ!」裕子の口から血反吐が溢れる。裕子はそのまま吹き飛ばされ、キャンバスに叩き付けられた。「あっ、グッ!」もはや裕子は仰向けに大の字になったまま身動きがとれなかった。裕子の左頬にはリングシューズの紐の痕が赤黒く刻印されていた。「反‥則…」ぼんやりとそう思ったが、レフリーは何もしようとしない。「ウオォン…」観客の歓声だろうか?遠くで声がする。海老塚がダウンした裕子に近づいてきた。「お馬鹿さん。あんなことで私に勝ったとでも思っているの。」勝ち誇った声に裕子の意識が次第に鮮明になる。「ち、畜生!」身をもたげようとしたが、全身が鉛でも埋め込まれたようにひどく重い。海老塚が更にもう一歩近づいた。「私に勝とうなんて一千億光年早いわよ!」そう言うと、裕子のトランクスをリングシューズで踏みにじった。「レフリーは何してんのよ!」裕子は縋るような目でレフリーを見た。「!」裕子は思わず声を飲み込んだ。そこには磯崎彩夏がレフリーの服装で立っていたのだ。海老塚が裕子のトランクスを踏んでいるにもかかわらず、カウントをとっている。「セブン、エイト」彩夏の声がする。「なぜ?彩ちゃんどうして!」裕子は叫ぼうとしたが全く声が出なかった。「ナイン、テン!!」彩夏はカウントを終了させると、海老塚の右腕を高々と上げた。裕子の目から大粒の涙がこぼれる。「彩ちゃん!どうして!?」そう叫んだ裕子の顔に何か、ざらついたものが擦りつけられた。
「ベロォン」何だか聞き覚えのある音だ。今度は目のあたりを通り過ぎた。「う、うぅん」
裕子は体を起こそうとしたが、身動きができない。「負けちゃったのか…えっ何?」意識が段々とはっきりしてきた。裕子が大の字になって涙まで流していたのは間違いないことだったが、そこはリングの上ではなく、自分のベッドの上だった。「なぁんだ、夢だったのか…」ほっとした裕子の顔をベッキーが不思議そうにのぞき込んでいた。「あんたが犯人ね!」『ダウン』した裕子が身動きすらできなかったのは、ベッキーが裕子の上で眠りこけていたせいだった。いくらベッキーが老犬だとはいえ、ゴールデンレトリバーにのしかかられては夢見のいいはずがない。裕子が体を起こすとベッキーが物憂そうに裕子の上から床に下り、大きなあくびを一つした。「何であんたがここにいるのよ!」裕子はそう言いながら、辺りを見回すともうすっかり陽が高く上っていた。「えっ!もうこんな時間?」裕子は寝癖頭を直すのもそこそこに、バッグに着替えを詰め込み、自宅を飛び出した。
「お前、その格好でここまできたのか?」ジムに着いた裕子をまず迎えたのは、後藤会長のこの一言だった。「寝癖!ボタンの掛け違え!」裕子の両手が頭から胸へ忙しく動いた。「全くもう、お前本当に女子高生か?」会長がさも呆れたように続けた。「会長それってあんまりじゃないですかぁ!」裕子が口を尖らせながら言った。「私これでも年頃なんですよ!」会長がジトッとした目で裕子を見た。「ふ〜うん。そうかそうか。なるほどねぇ。」会長の視線が裕子の足元に向けられている。会長の視線をなぞった先にはソックスがあった。右は黒いラインが一本は入り、左は無地の純白のソックスだった。「あっ、ええと。あはははは…」ここまでくると笑うしかない。
「そんなことじゃぁ光鳴に勝てないぞ」会長の言葉に頬をかいていた裕子の手が止まり、表情がキュッと引き締まった。「えっ!それじゃぁ次の試合もしかして?その…」「そう!そのもしか。でもこれじゃぁなぁ」後藤の口元に悪戯っぽい笑みが浮かんだ。「大丈夫ですよ!いやったぁあ!」裕子は歓声を上げ、会長の大きな手を取ってダンスを踊るようにステップを踏んでいた。自分が妙ちくりんな格好でジムまで来てしまった恥ずかしさなどとっくに頭の中から蒸発していた。「おいおい、裕子。」会長は苦笑いを浮かべていたが、会長自身この一戦には思うものを胸に秘めていた。裕子の三戦目。勝利を味あわせようと組んだはずが、結果は最悪の、裕子自身が引退すら考えるほど無様なKO負けだったのだ。会長自身も自らの判断の甘さに忸怩たる思いがあった。「おい、喜ぶのはこの辺にしてトレーニングの準備だ。明日はお客さんも来るんだからな。さっさと着替えろ!」会長にそう言われ、裕子はもう一度自分の格好を見回すと、更衣室に慌てて飛び込んだ。
更衣室で裕子は真っ先に携帯を取り出し、器用な手つきでメールを打ち始めた。
『次の対戦相手が決まりました!光鳴聖選手。私が3試合目で負けちゃった(T_T)相手です。彩ちゃんもいよいよチャンピオン目前!明日からの「秘密特訓合宿」頑張りましょう!!それでは明日、駅で待ってま〜す(^_^)/~』
「よーし!送信っと。」裕子は磯崎彩夏に宛てたメールを送信すると携帯をたたみ、バックの中に入れた。「秘密特訓合宿」とは、いかにも裕子らしい洗練されない言い方だが、また彩夏と会えると思うと気持ちがうきうきするのを禁じ得なかった。裕子は現在9戦6勝3敗、全試合KO決着という、これまたらしいといえばらしい戦績だった。この3敗は、デビュー戦で今メールを送った彩夏に逆転のKO負けを喫し、その後連敗したものだ。特に今回再戦が決定した光鳴聖に敗北した試合は、裕子に引退まで決意させたほどの無様な敗北だった。「あの時…」裕子はこの試合を鮮明に思い出すことができた。
「負けたらすべてが終わる!」正確に言えば、裕子は光鳴に敗北したと言うより、この気持ちにがんじがらめにされ、すべての攻撃が空回りした結果、光鳴のパンチに身を刻まれたと言ってよかった。冷静さを完全に失い、右腕を振り上げた瞬間、裕子の鳩尾に光鳴のボディアッパーが深々と抉り込まれていた。「ウゲェッ!」あの声は自分の声じゃないみたいだった。相手の真っ赤なトランクスが、視界一杯に広がり、「聖」と刺繍された字が脳裏に焼き付いた。次の瞬間には光鳴のリングシューズの前に這い蹲っていた。「負けたくない!」意識がいかに叫んでも体が言うことを聞かなかった。懸命に立ち上がろうとしたが、自分がKOされたことを悟った瞬間、キャンバスに大の字になったままマウスピースを高々と吹き上げ、無様に悶絶していた。大歓声に包まれる会場から担架で運び出されながら、タオルをかけられた下で裕子は涙を抑えることが出来なかった。
こんな無様なKOシーンは稀だと言っていい。格闘雑誌にもこのシーンが大きく取り上げられ、裕子の精神状態はどん底だった。そんな裕子を救ってくれたのは、他ならぬ彩夏の言葉だった。「もう一度戦わないことには納得できない!」今をときめくKOプリンセスの一言が裕子に新たな活力を吹き込んでくれた。『ブラッディマリー』海老塚万里子をKOで沈め、以後の連勝のスタートを飾ることができた。ランキング10位!何だかそんな自分が信じられない!彩夏と対戦しなかったら、間違いなく中途半端で満足し、つまらない敗北でボクシングを投げ出していたに違いない。その意味で彩夏は裕子にとって何にも代え難い恩人だった。
それと同時に光鳴聖にも大きな負債があった。「あの時負けたのは自分じゃない!」負け惜しみのようだが、そう思えてならない。すべてが空回りする焦り、鳩尾に抉り込まれたパンチのダメージ、無様に腫れ上がった顔を血反吐まみれにしたKO負け!「あの時…」すべての歯車が狂っていた。本当にそう思う。『負け惜しみだ』という奴には言わせておけばいい!今回の対戦でそんな自分自身に決着をつけたかった。今日この対戦が決まった時、裕子は自分の血が燃え上がるのを確かに感じた。
家に帰ってからもなかなか寝付かれなかった。彩夏に会える喜びと、光鳴との再戦が決定した興奮で気持ちがいつになく高揚していた。「明日からのメニューはどうしようか?」裕子はベッドに横になりながら考えた。女子のボクシングもインターハイの正式種目になり、裾野がひろがりつつあるとはいえ、裕子はもちろん彩夏にとっても同レベルで練習ができる選手の存在は貴重だった。今回は夏休みを使った4泊5日の「強化合宿」だ。特に今年は裕子も彩夏も受験生であり、ボクシングだけでなく学力の向上も課題の一つだった。「ランニングと、そうそうスパーリングはこの前みたいにジムを借りればいいか。ようし!国語は彩ちゃんに教わろう!!」どうも国語って奴は分からない。なんであんなにスパッと行かないものを勉強しなくちゃならないのよ!これは完全に裕子の負け惜しみなのだが、裕子にとって彩夏はボクシングだけでなく、国語についても最高の『教師』だった。「うん!これでおっけー!」そう独り言を言うと、裕子は枕元のライトの紐を引いた。